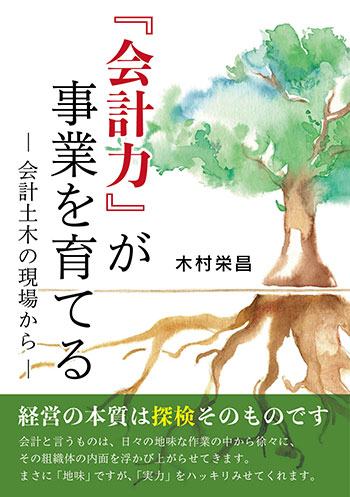| NEWS |
NEWS 「冬の時代を笑いで乗切るために」シリーズの新しい物語が始まりました。これからも多くなると思われるM&Aを素材にしています。現代の人間欲が凝縮されたのが実際のM&Aです。争いの実例は生々しいですがワカリヤスク見どころのみアクぬきしました。仕事現場でも成功の話より失敗例を聞くことの方が多いです。お役に立てれば何よりです。犬猫漫談・・2.26事件 猫納言:2月26日は、おとといだったね。 犬式部:それがどうした? 猫納言:1936年(昭和11年)2.26事件が起こった時は前回の15年戦争小史では 戦争始まっていたのだね。反乱部隊の出身地は東北が多く、悲惨だった と。 犬式部:ボスに聞いたが都会で働く人も低賃金でご飯が食べられなくて兵営の 残飯をもらって飢えをしのいだらしい。中でも近衛師団の残飯が一番 「質」が良くて人々が殺到したらしい。近衛師団は天皇陛下をお守りする からエリートなのね。 猫納言:あの本で思い出した。ボスが言われるには1945年2月にヤルタ協定が連 合国で結ばれた。この時に降参していたら沖縄戦も東京その他大空襲も原 爆投下もソ連侵攻も起こらなかったかも、と。その上、「なんら憲法上の 根拠のない御前会議という非立憲的手続きによって重大な最高方針の決定 を重ねたのである。」(同書333頁)と堂々と書かれているらしい。更に 終戦後満州に置き去りの日本人はソ連に対するカムフラージュで案山子な いし盾にされたとも書かれている、317頁。本当のことが分かると、、 犬式部:今も戦争に負けたことが尾を引いて米国の言いなり、おカネ30兆円持っ て行かないかんなど。株が上がったのはアメリカの株高の恩恵で上がって るのだろう。政府のカモフラージュを見抜いて行動しないとエライ目に遇 うね! 猫納言:ボスによれば、昔は軍部、今は経済団体の動きを注意することらしい。 犬式部:シツ、ボスが来た。寝たフリしよう。 猫納言:それが良い!
» 過去のNEWS
|
|---|---|

|
冬の時代を笑いで乗切るために—<短編物語>読むだけで税や会計の生きた知識が不思議に身に付く—
はじめに
風変わりな題名はM&A(合併&買収)において当事者は大変な思いをされておられますが、見方を変えますと「問題の松花堂弁当ないしは缶詰詰合せ」のようなところがあります。日常では現われてこない複雑な問題が混在しています。
時代が大きく変わり、事業の経営も急ピッチで新旧交代を余儀なくされます。
これからもM&A(合併、買収だけではなく会社分割、事業譲渡も含めます)を選択される件数は増加することはあっても減少することはないと思います。
AIとの対話反復でプロンプトスキルを磨く—難題解決の決め手—
プロンプトに関するセミナーや書物はたくさん出ています。この項目は
それらに重複する部分には触れません。
矛盾と勢い:孫子で打つ手が見えてくる—2500年の智恵を生かす不敗の道—
いま思いつくのは下の3人です。
徳川家康、武田信玄、楠木正成
重加算税:知ると知らないで大違い!—無知ほどコワイものはない—
重加算税がかかれば今後の税務調査が早く来ると思ってください。税務署は不正行為をする者には強い姿勢です。前科のようにずっと祟るものではなく一定期間は税務署からキビシク見られます。
重加算税がかけられる前に税務署内で署長、副署長、幹部職員が参加する「重要事案審議会」での決済を経ます。過少申告加算税と違い文字通り重い処分です。
税務トラブルのご相談
税務当局から指摘を受けトラブルになった場合、知識と経験を生かして税務当局と調整・交渉を行ないトラブルの収束に努めます。損失を最小限にとどめるよう尽力します。